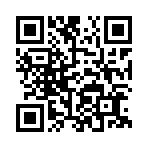2010年03月31日
塀! Hey! 塀!
関ヶ原に敗れた毛利輝元が築城・開府して依頼200年以上も毛利氏36万石の城下町として栄えた萩市。城下町らしい面影を今も残しています。重要伝統的建造物群保存地区に指定されている街並みは、伝統建築の外観、納まり、素材などの勉強にもってこいです。今回は塀について...

これは商家であったところです。純白の漆喰、ランダムな窓、なまこ壁が特徴です。なまこ壁とは平たい瓦を壁に敷き詰め、なまこのような断面の半円状に漆喰で目地をかたどったものです。

こちらは武家屋敷の典型的な塀です。瓦、漆喰、木板、石垣のコントラストがかっこいいです。この周辺には、高杉晋作や木戸孝允の生家もあり、幕末好きにはたまりません。萩市は伊藤博文の出身地でもあり、吉田松陰の松下村塾もありました。幕末の中心人物となった国を動かした人々の出身地です。すごい萩市。

こちらは萩の象徴的な土塀と夏みかん。この組み合わせなんとも言えない、いい感じがします。この辺りには、鍵曲と呼ばれる鍵の手に曲がった通路が多くあり、見通しを悪くする軍事的目的でつくられた道路形態だそうです。ちなみに、現地でかった夏みかんドレッシング、相当美味かったです。

この辺りは、藍場川といい藍染めを川でおこなっていたことからこの名前がついたそうです。今ではこの水路には鯉が泳いでいます。塀は焼杉かと思われます。
同じ町でも塀ひとつとってもそれぞれ趣が違います。また、本物の素材、石や土や木などを使用してつくられたものは何百年経っても味があって美しい。こういうところでは、経年美というものを実際に見て学べます。これからも古い街並みを探訪して学びたいと思います。

これは商家であったところです。純白の漆喰、ランダムな窓、なまこ壁が特徴です。なまこ壁とは平たい瓦を壁に敷き詰め、なまこのような断面の半円状に漆喰で目地をかたどったものです。

こちらは武家屋敷の典型的な塀です。瓦、漆喰、木板、石垣のコントラストがかっこいいです。この周辺には、高杉晋作や木戸孝允の生家もあり、幕末好きにはたまりません。萩市は伊藤博文の出身地でもあり、吉田松陰の松下村塾もありました。幕末の中心人物となった国を動かした人々の出身地です。すごい萩市。

こちらは萩の象徴的な土塀と夏みかん。この組み合わせなんとも言えない、いい感じがします。この辺りには、鍵曲と呼ばれる鍵の手に曲がった通路が多くあり、見通しを悪くする軍事的目的でつくられた道路形態だそうです。ちなみに、現地でかった夏みかんドレッシング、相当美味かったです。

この辺りは、藍場川といい藍染めを川でおこなっていたことからこの名前がついたそうです。今ではこの水路には鯉が泳いでいます。塀は焼杉かと思われます。
同じ町でも塀ひとつとってもそれぞれ趣が違います。また、本物の素材、石や土や木などを使用してつくられたものは何百年経っても味があって美しい。こういうところでは、経年美というものを実際に見て学べます。これからも古い街並みを探訪して学びたいと思います。
数寄屋研究 Sukiya study
プレハブ式茶室住宅 Construction completed
Churches of Japan
Traditional Japanse house
Soil investigation
Learn from traditional design
プレハブ式茶室住宅 Construction completed
Churches of Japan
Traditional Japanse house
Soil investigation
Learn from traditional design
Posted by Masakatsu Nishitani at 20:11│Comments(2)
│ジャポニズム復興運動 Japonism
この記事へのコメント
萩市。。中学の修学旅行の一度きりです。
あの頃は歴史とも建築とも無縁だったのでほとんど記憶無し;;
趣のある景観ですね~~
一日ぶらぶらと歩いて回りたいです^^
あの頃は歴史とも建築とも無縁だったのでほとんど記憶無し;;
趣のある景観ですね~~
一日ぶらぶらと歩いて回りたいです^^
Posted by まろ at 2010年03月31日 21:57
まろさん、萩市が修学旅行ってせつないですねー。大人の旅用の町でしょうに。そら記憶ないでしょうな。ほんまぶらぶら歩きまわるにはもってこいの町ですよ。
Posted by にしなっつ at 2010年03月31日 23:51
at 2010年03月31日 23:51
 at 2010年03月31日 23:51
at 2010年03月31日 23:51