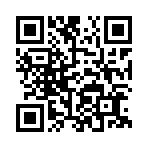2010年12月23日
ひっかいて絵を描く...
先日、自身のブログでベルナール・ビュフェさんというフランスの画家を紹介しました。ひっかいたようなタッチで絵を描いてはる人で、すごく魅力的な絵やと思たんです。それでこういう風にして描いてみたいと思ったんです。

今週の日曜日は、ラグビーの全国大会初戦を控え、ピリピリしていたので、うさちゃん、描くことにしました。ひっかくと言えば幼稚園の時にやった"ひっかき絵"。色のついたクレヨン塗りたくって、その上に黒のクレヨンで覆った後、割り箸なんかでひっかいて絵を描いてたやつです。普通、黒で覆うんですけど、白で覆いたかったんで、白のクレヨン塗ったくりましたところ、そんなに白くならなかったので、更にアクリル絵の具の白を被せたんです。そして、割り箸を削って尖らせ、絵を描きました。まだまだビュフェさんのようにはいきませんが、こうやって新たな表現方法を身に付けたいです。

今週の日曜日は、ラグビーの全国大会初戦を控え、ピリピリしていたので、うさちゃん、描くことにしました。ひっかくと言えば幼稚園の時にやった"ひっかき絵"。色のついたクレヨン塗りたくって、その上に黒のクレヨンで覆った後、割り箸なんかでひっかいて絵を描いてたやつです。普通、黒で覆うんですけど、白で覆いたかったんで、白のクレヨン塗ったくりましたところ、そんなに白くならなかったので、更にアクリル絵の具の白を被せたんです。そして、割り箸を削って尖らせ、絵を描きました。まだまだビュフェさんのようにはいきませんが、こうやって新たな表現方法を身に付けたいです。
Posted by Masakatsu Nishitani at
21:22
│Comments(4)
2010年12月22日
体育会系、肥前浜宿をゆく

日本の伝統建築の勉強のため、古い街並みを渡り歩いています。佐賀県の肥前浜宿を訪ねました。ここは江戸時代に長崎街道の宿場町として栄え、明治以降も酒造業や水産業に支えられ豊かな街並みがつくられたそうです。土蔵造りや茅葺町家が建ち並び、今もその名残を垣間見ることができます。

南舟津という場所の茅葺き屋根の住宅が改築されていました。茅葺は葺き替えが大変ですけど、あたたかい気持ちになります。

旧乗田家住宅という武家屋敷。漆喰が新たに塗られて綺麗でした。ここはクド造りくど造りは、小さな屋根を組み合わせ、棟(むね)が、T、L、冂などの形になっています。かまどを上から見ると、漢字の冂(けいがまえ)に見えます。下の方が焚き口です。かまど(竈)のことを、「くど」と呼ぶことから「くど造り」と言われるようになりました。
建築のデザインにしろ、納まりにしろ、こうやって原点に立ち帰り、アイディアやヒントを教えてもらうようにしてます。また、何十年も何百年も経った家から、経年後の建材の様子やメンテナンスの大切さを学ぶこともできるのです。こういう旅、とても大事にしています。
Posted by Masakatsu Nishitani at
00:48
│Comments(0)
2010年12月17日
滅びゆく美

アンティーク・古材・廃材の経年美を追い求めてぐるぐる回っています。ここの業者さんは、世界中を回っては、古い倉庫、屋敷を丸ごと買い取り、分解して日本に持ち帰り、こうやってお店で見せてくれるんです。こういった古材の味は、歴史を重ねないとでないもので、どうやっても作り出せないんですよね。

ドアノブやカギ穴などの小物もズラリ。ここにいるとすごくアイディアが触発されてワクワクしてしまうんです。前方後円墳の形した鍵穴ありますでしょ、あれにかなり魅かれるんです。

ある建築家の言葉で、「古い家には新築には望めない「滅びゆく美」がある。それを惜しむ心があれば残す方に心が傾く。」というのがあります。滅びゆく美を惜しんでいるこういうお店を訪ねては、そこからアイディアをもらって、永く惜しまれるようなデザイン、素材選びに生かしていきたいと思うのであります。滅びゆく美を求めて、これからもこういうところに通う。
Posted by Masakatsu Nishitani at
12:09
│Comments(2)
2010年12月16日
ひっかいたような作品集

先日、自身ブログで紹介したのですが、一目惚れした絵がありまして、即行その画家の作品集を買いました。ベルナール・ビュフェという画家さんの作品集「ビュフェとアナベル」です。これ、ただの作品集ではありませんでした。

タイトルにもあります、アナベルさんというのが彼の奥さんで、彼と彼女の生い立ち、出会い、共に生きた41年の歳月について小説のように描かれているんです。ビュフェはこのアナベルをモチーフにした作品を多く描いたようで、この作品集のほとんどが彼女を描いたものです。同じ人の絵を何枚も描くなんて、なかなかできないですよ。よっぽど好きやったんでしょうね。

写真なんかもあったりして、この写真、ビュフェとアナベルが運命的な出会いをしたその瞬間をとらえたものだそうです。羨ましい...

こんなポスターのような作品もあり。この力強い線がカッコいいんですよね。下の絵のような絵本チックなようなのもあり。こういう絵描いてみたいんですよね。オイルパステルかクレヨンなんかでこんな感じが出るような気がします。自分の手描きパースも彼の画法を取り入れて描いてみようと思います。

ビュフェは晩年、パーキンソン病を患い、71歳で自ら命を絶ったそうです。「絵は私の命です。これを取り上げられてしまったら生きて行けないでしょう。」という彼の言葉。そのくらいの気持ちで大好きな絵に、建築に一生懸命取り組んでみたいものです。ビュフェとアナベルの深い愛情を中心にドラマチックで小説のような作品集でした。ただの作品集やないですよ。
Posted by Masakatsu Nishitani at
17:50
│Comments(2)
2010年12月15日
木船の木 ~棟梁のコダワリ~
古民家改築プロジェクト"one stubborn grandpa and eel's bed"(長いでしょ)、田川郡福智町にて進行中です。現在、躯体工事、金物補強をおこなっております。この段階では柱、梁、間柱、胴縁など、壁の中に入って見えなくなる部分の木組みがおこなわれています。杉の木が主に使用されるのですが、この現場の棟梁にはコダワリがありました。

今回は、この現場の大工棟梁が、"飫肥杉"という材料を使用してくれていました。宮崎の日南で生育される杉で、江戸時代にここにあった飫肥藩によって植林が始められた歴史のある材料です。棟梁がこの木にコダワルのには理由があります。

この地方で伐採される杉には、樹脂が多く含まれているため吸水性が低く、軽量で強度が高いことから造船用として盛んに利用されていたそうです。つまり、耐久性のある良質な木を使いたいというのがこの棟梁のコダワリだったのです。こちらからは何も指示していません。棟梁が自発的にこういった材料を選んでくれていた訳です。これは大工としての"差別化"だそうです。

木船の木で古民家改築中です。古き良きものをより永く生かす、その為に材料にもコダワル。リノベーションの真骨頂ですね。
コダワリをもつ棟梁のブログはコチラ ⇒ 大工魂(だいくこん)

今回は、この現場の大工棟梁が、"飫肥杉"という材料を使用してくれていました。宮崎の日南で生育される杉で、江戸時代にここにあった飫肥藩によって植林が始められた歴史のある材料です。棟梁がこの木にコダワルのには理由があります。

この地方で伐採される杉には、樹脂が多く含まれているため吸水性が低く、軽量で強度が高いことから造船用として盛んに利用されていたそうです。つまり、耐久性のある良質な木を使いたいというのがこの棟梁のコダワリだったのです。こちらからは何も指示していません。棟梁が自発的にこういった材料を選んでくれていた訳です。これは大工としての"差別化"だそうです。

木船の木で古民家改築中です。古き良きものをより永く生かす、その為に材料にもコダワル。リノベーションの真骨頂ですね。
コダワリをもつ棟梁のブログはコチラ ⇒ 大工魂(だいくこん)
Posted by Masakatsu Nishitani at
15:01
│Comments(0)
2010年12月14日
地球温暖化で伸びたい
エコ住宅、つまり環境建築の勉強中です。「地球温暖化で伸びるビジネス」(日本総合研究所著)を読みました。地球温暖化の問題を糧に金儲けしたいという気持ちからではありません。これから環境問題改善の手法が広まっていくには、ビジネスとして成り立たなくてはいけません。慈善ではできないし、広まってもいかない。環境改善をビジネスへとつなげていく手法のヒントがあると感じたので、この本を入手しました。

この本の文中に、EU市民の地球環境に対する意識は高く、国が環境政策を織り込んでいることにより環境ビジネスが成長している。一方、日本では企業が地球温暖化を経営戦略のレベルで吟味することがなされず欧州企業に後れをとっているということです。日本の技術力を結集すれば、後れをとることなんてないはずなのに...
その他にも、地球温暖化を意識しない自動車開発をおこなうことは、将来的にはできなくなると予測している節がありました。建築もしかりだと思います。環境を意識しない建築はできなくなるのでは...
建築に関連することも含まれていたのですが、住宅消費者の住宅購入時におけるポイントについてのグラフが記載されていました。消費者が重視している項目として、耐震性、遮音性、耐久性、防犯性、日照というものが挙げられていました。しかし、省エネ効果が期待できる断熱性が低いのが意外でした。その理由として、「効果がわらりづらい環境面に配慮した機能は消費者に軽視される...」ということ。提案側がわかりやすく説明しきれていないっていうのがすごくあるんじゃないかなと思うんです。
今後は、省エネ機器や設備に関する知識や経験が豊富で、適切なアドバイスをおこなうことのできるコンサルティング能力を持つ建築業者やリフォーム業者に優位性がでてくるとのことです。自分自身もそうなりたいと思っています。その為にも、継続して環境建築の勉強を続けていきます。

この本の文中に、EU市民の地球環境に対する意識は高く、国が環境政策を織り込んでいることにより環境ビジネスが成長している。一方、日本では企業が地球温暖化を経営戦略のレベルで吟味することがなされず欧州企業に後れをとっているということです。日本の技術力を結集すれば、後れをとることなんてないはずなのに...
その他にも、地球温暖化を意識しない自動車開発をおこなうことは、将来的にはできなくなると予測している節がありました。建築もしかりだと思います。環境を意識しない建築はできなくなるのでは...
建築に関連することも含まれていたのですが、住宅消費者の住宅購入時におけるポイントについてのグラフが記載されていました。消費者が重視している項目として、耐震性、遮音性、耐久性、防犯性、日照というものが挙げられていました。しかし、省エネ効果が期待できる断熱性が低いのが意外でした。その理由として、「効果がわらりづらい環境面に配慮した機能は消費者に軽視される...」ということ。提案側がわかりやすく説明しきれていないっていうのがすごくあるんじゃないかなと思うんです。
今後は、省エネ機器や設備に関する知識や経験が豊富で、適切なアドバイスをおこなうことのできるコンサルティング能力を持つ建築業者やリフォーム業者に優位性がでてくるとのことです。自分自身もそうなりたいと思っています。その為にも、継続して環境建築の勉強を続けていきます。
Posted by Masakatsu Nishitani at
13:35
│Comments(0)
2010年12月10日
ひっかいたような絵

引っかいたようなタッチで描いた絵に出会いました。版画のような感じにも見えます。僕もこんな風に力強いタッチの絵を描いてみたかったんです。とても魅かれました。早速、アマゾンで画集を発注。お金ないのに。

この絵は戦後を生きたフランスの画家、ベルナール・ビュフェさんの作品です。絵画的に分類しますと具象絵画といいまして、対象物を具体的に描いたものです。インパクトがあってカッコいい絵ですよね。

建築物も多く描いているのです。このモノクロ感も彼の特徴であります。線が力強いと見ててもなんか気持ちいいです。次の建築プレゼンはこのスタイルでパースを描くことにします。どうやって描いているのか謎なんですが。決してパクるのではありません、吸収するのです。
Posted by Masakatsu Nishitani at
18:26
│Comments(1)
2010年12月09日
瞬く間の里帰り...

一瞬、ふるさと神戸に帰りました。商船三井ビルヂング、ここはいつ見てもカッコいい。幼い頃からここを見るといつもそう思います。竣工は1922年だそうで、もう90年近く経つのにこんなにカッコいい。鉄骨鉄筋コンクリート造ですが、外壁にかなりデカイ石が積まれています。やはり石の建築はいい。経年美と重厚感、そして歴史が感じられます。

一瞬帰省の目的は、スカンジナビアン・リビングさんというこのビルに入っているデンマーク建築をやってらっしゃる会社を訪問しました。国民のエコロジーに対する意識が高いデンマークの建築、建材を広めていこうという働きかけを学んできました。オフィスにあった数々のデンマーク家具。カッコいいです。やっぱ、ふるさと神戸はなんでもカッコええなぁ~。デンマークをはじめとするエコ建築、本格的に勉強しています。

ミーティングが終わり、神戸と言えば多国籍料理へ。今回はトルコ料理店でケバブをほおばり、トルコアイスを伸ばし、あたふたしながら即福岡へ。今回の里帰り。瞬く間でした。ルミナリエがせつなく輝いていました。
Posted by Masakatsu Nishitani at
23:59
│Comments(8)
2010年12月07日
体育会系、環境共棲を考える。
吉田桂二さんという建築家がいらっしゃいます。環境共棲住宅を提唱、日本の伝統建築を後世に伝承する取り組みをされています。この方の想いには共感するところが多く、よく本を読んでは勉強させてもらっています。今回は「家づくりの知恵-エコロジーの住まいとは何か」という吉田さんの著書を読みました。

「高気密高断熱の家にして24時間空調生活を強いる家がなんでエコロジーなんだ!!」と憤りを感じられるような文章がありました。現在の住宅には、エコの代名詞として"高気密高断熱"という言葉が使われていますが、この建築家さんはそれに憤りを感じてはるんです。
昔の日本の家には、設備も機械も何もない時代に、日照、通風、採光、換気をいかにおこなうかという知恵がありました。それは開放的なお家です。一方、現代の家は、断熱、気密、耐震、耐久の時代へと誘導され、おのずと密閉生活を強いられていると。密閉すると夏はどうすんだと。暑くてエアコンに頼るしかないじゃないか、これはエコロジーとは正反対やないかー!ってことなんです。
先日、僕も断熱材やサッシの性能でどれだけ光熱費が削減できてエコがという勉強をしてきてたんです。この本を読み終わったばかりなんで、悩んでいます。でも、やはりこの著者に賛同したい。設備や建材、その性能が重視されてばかりで、自然の力を理解し、利用することがおろそかになっているんじゃないかと思うんです。
もう一度、"日本の家"に立ち返る重要性を胸に...

「高気密高断熱の家にして24時間空調生活を強いる家がなんでエコロジーなんだ!!」と憤りを感じられるような文章がありました。現在の住宅には、エコの代名詞として"高気密高断熱"という言葉が使われていますが、この建築家さんはそれに憤りを感じてはるんです。
昔の日本の家には、設備も機械も何もない時代に、日照、通風、採光、換気をいかにおこなうかという知恵がありました。それは開放的なお家です。一方、現代の家は、断熱、気密、耐震、耐久の時代へと誘導され、おのずと密閉生活を強いられていると。密閉すると夏はどうすんだと。暑くてエアコンに頼るしかないじゃないか、これはエコロジーとは正反対やないかー!ってことなんです。
先日、僕も断熱材やサッシの性能でどれだけ光熱費が削減できてエコがという勉強をしてきてたんです。この本を読み終わったばかりなんで、悩んでいます。でも、やはりこの著者に賛同したい。設備や建材、その性能が重視されてばかりで、自然の力を理解し、利用することがおろそかになっているんじゃないかと思うんです。
もう一度、"日本の家"に立ち返る重要性を胸に...
Posted by Masakatsu Nishitani at
16:28
│Comments(0)
2010年12月05日
楓には日本庭園がよく合う。

うちの近所のお寺にはこんなすごい紅葉の木があります。カエデだそうで、樹齢400年とか。圧倒されます。

やっぱり日本庭園には楓や紅葉が合うなぁと思いつつ、今、進行中のプロジェクトでもイロハモミジのあるデッキスペース検討中でしたが、やっぱ石と苔が合うなぁ。お客さんに提案してみます。ちなみにカエデとモミジって植物学的には同じ木みたいですね。葉の形が異なっているだけで、モミジの方が葉の谷が深い、一方のカエデは浅い。英語ではどちらもmapleです。シロップたっぷりのホットケーキ食いてー。

こんな近所にこんな小京都があるとは。寺社の建築物は勉強になりますし、毘沙門天や不動明王などの仏像には身震いさせられました。自分でつくってみたい...
Posted by Masakatsu Nishitani at
00:17
│Comments(2)
2010年12月02日
工房を訪ねる。
同業者であります、あるハウスメーカーというより"工房"の設計の方と知り合う機会がありまして、早速、そちらの住宅展示場訪ねさせて頂きました。こちらの工房のコダワリを色々と学びたかったのです。

ウィルウォール(高い...)という木板を鎧張りという張り方で外壁に使用しています。この張り方、好きです。もう6年目の外壁ですが、塗装も剥げて味のあるいい感じになっています。

そのコダワリのひとつが、家の構造材に国産の燻煙処理木材を使用していること。地産地消で地元九州の木を生かし、燻煙により変形の少ない、木の特性を生かした乾燥方法を採用されています。古民家の囲炉裏の煙にいぶされた木材のように、耐久性のある防腐防虫効果もある木になるそうです。手間かかってますねー。

そして、断熱材は僕の住んでいたニュージーランドから輸入した羊毛。自然素材で、見るからに暖かそうです。この羊毛は吸放湿性があります。あまり湿気を吸着しすぎると羊毛が落ちてきたり、断熱性能が落ちたりするのですが、そこに調湿建材を設置し、その問題をカバーしています。こちらの工房は、上の木材と合わせてこれを標準仕様にしています。手間もお金もかかるけど、材料に自信があるからこそそういうふうにできるんでしょう。

こちらの工房も専門の職人がつくったステンドグラスを取り入れているようで、素晴しい作品がありました。無名のステンドグラス職人の私も刺激を受けたのであります。しかし、僕のステンドグラスの特徴は粗削りな素朴さにあります。こんなに綺麗には作れないけど、味は出せます。負けじと頑張ります。

ウィルウォール(高い...)という木板を鎧張りという張り方で外壁に使用しています。この張り方、好きです。もう6年目の外壁ですが、塗装も剥げて味のあるいい感じになっています。

そのコダワリのひとつが、家の構造材に国産の燻煙処理木材を使用していること。地産地消で地元九州の木を生かし、燻煙により変形の少ない、木の特性を生かした乾燥方法を採用されています。古民家の囲炉裏の煙にいぶされた木材のように、耐久性のある防腐防虫効果もある木になるそうです。手間かかってますねー。

そして、断熱材は僕の住んでいたニュージーランドから輸入した羊毛。自然素材で、見るからに暖かそうです。この羊毛は吸放湿性があります。あまり湿気を吸着しすぎると羊毛が落ちてきたり、断熱性能が落ちたりするのですが、そこに調湿建材を設置し、その問題をカバーしています。こちらの工房は、上の木材と合わせてこれを標準仕様にしています。手間もお金もかかるけど、材料に自信があるからこそそういうふうにできるんでしょう。

こちらの工房も専門の職人がつくったステンドグラスを取り入れているようで、素晴しい作品がありました。無名のステンドグラス職人の私も刺激を受けたのであります。しかし、僕のステンドグラスの特徴は粗削りな素朴さにあります。こんなに綺麗には作れないけど、味は出せます。負けじと頑張ります。
Posted by Masakatsu Nishitani at
20:32
│Comments(0)